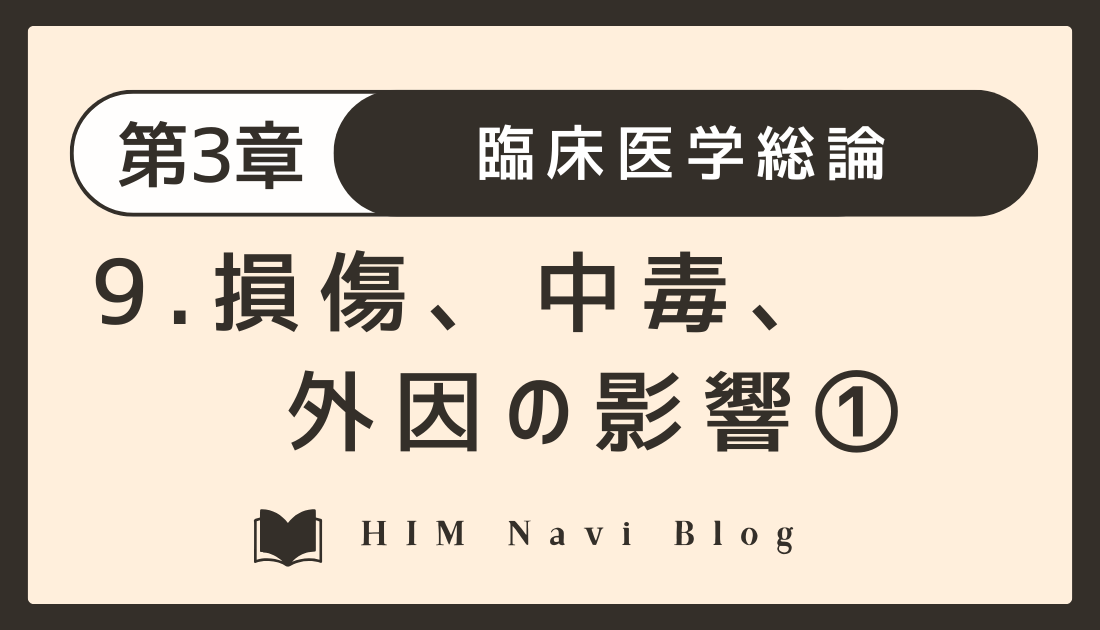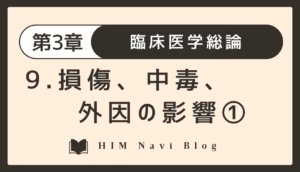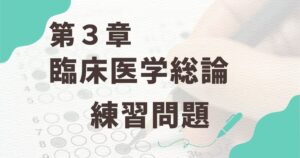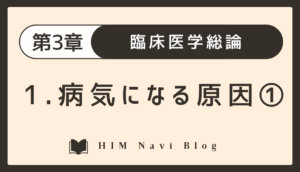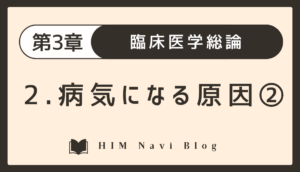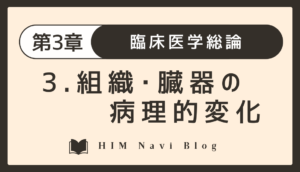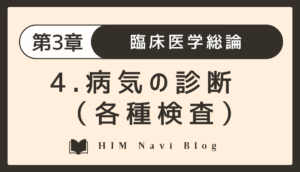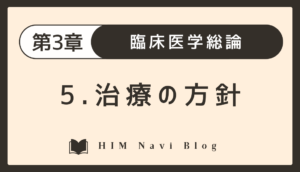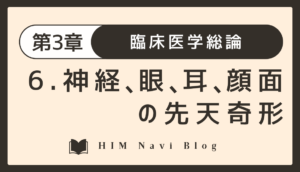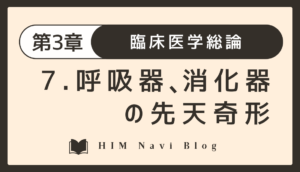目次
損傷、中毒、その他の外因の影響(S00-S98)
軟部組織の損傷
皮膚損傷
| 疾病 | 特徴 | 特記事項 |
| 擦過傷(擦過創) | 表皮剥離による「すりきず」。疾痛が強く、時間とともに痂皮で覆われ治癒する。跡がほとんど残らない。 | – |
| 切創 | 鋭利な刃物で切断され、創縁が平滑。出血は多いが、疾痛は少ない。 | 血管や神経が鋭利に切断される。 |
| 挫傷・挫創 | 鈍器による損傷。挫傷は皮膚に創がなく、挫創は開放創がある。創縁・創面は不規則。疾痛は強く、出血は少ない。 | 腱や神経、血管の損傷、場合によっては骨損傷も伴う。 |
| 刺創 | 刺入口は小さいが、創が深く、内臓器の損傷が伴いやすい。 | 内臓損傷のリスクが高い。 |
| 割創 | 切創と挫創の中間的な性質を持つ。骨など堅い組織の上に鈍的な圧力が加わり皮膚に断裂が生じる。 | – |
| 銃創 | 弾丸による損傷。盲管、貫通、擦過の形態がある。 | – |
| 咬創 | 人や動物に咬まれて生じた創。感染のリスクが高い。 | 感染症のリスクに注意。 |
| 開放創の治療 | 感染防止と一次治癒を目指す。受傷後6~8時間以内に徹底洗浄し、壊死組織をデブリードマン後、一次縫合する。 |
デブリードマン不完全時は二次縫合や遷延縫合を行う。 |

覚え方のアドバイス
外傷や疾病の特徴を覚えるには、以下の方法が効果的です。
- 類似した外傷の比較で覚える:例えば、切創と刺創、挫傷・挫創のように似ているけれど異なる部分を比較しながら覚えると、違いが分かりやすくなります。刺創は小さいけれど深く、切創は平滑であることに注目!
- イメージで覚える:外傷の説明を頭の中でイメージすることが大切です。例えば、「擦過傷」は「すりきず」として自分の経験と結びつけると覚えやすくなります。また、刺創は「針のように深く刺さる」イメージをもって覚えると頭に残りやすいです。
- ストーリーを作る:それぞれの外傷の治癒過程や治療法をストーリー化して覚えるのも有効です。例えば、「咬創は感染のリスクがあるから、しっかり洗浄してから縫合する」といった具体的な流れを想像しながら学ぶと効果的です。
暗記は少しずつ進めていくことが大事です。楽しみながら覚えていきましょう!
筋・腱損傷、血管損傷、靭帯損傷、
| 病名/損傷 | 特徴 | 特記事項 |
| 開放性筋・腱損傷 | 皮膚損傷が筋肉や腱に及んだ状態。切創や挫創などの開放創がある。 | – |
| 閉鎖性筋・腱損傷 | 筋肉の急激な収縮や鈍的外力によって発生。スポーツ外傷が多い。 | – |
| 筋断裂 | 完全断裂と不完全断裂があり、不完全断裂は「肉ばなれ」と呼ばれる。大腿四頭筋、膝屈筋、腓腹筋に多い。 | 治療法:軽・中度の場合テーピング、不十分な場合は副子固定。完全断裂では縫合と外固定。 |
| 腱断裂 | スポーツや退行変性疾患、慢性関節リウマチ、骨折で発生。肩腱板やアキレス腱などが好発部位。 | 治療法:アキレス腱断裂ではギプス固定。手の皮下腱断裂は縫合または腱移行術。専門的治療が必要。 |
| 血管損傷 | 労働災害や交通事故で発生。閉鎖性は骨折や脱臼に伴い、開放性は切創や挫滅創に伴う。 | 治療法:動脈損傷は縫合が必要。静脈損傷は結紮処置で十分なことが多い。血管障害が疑われる場合は開創手術が必要。 |
| 靭帯損傷 | 関節に過剰な運動が加わり靭帯が損傷。膝関節、足関節に多い。部分断裂(捻挫)から完全断裂までの分類。 | 治療法:部分断裂は湿布・テーピング。中等度以上は固定。完全断裂は手術が必要。 |

覚え方のアドバイス
外傷や損傷の特徴を効率よく覚えるには、以下のポイントを押さえて学習を進めるのが効果的です。
- 関連部位を意識してグループ化する
筋肉・腱・靭帯など、同じような部位に起こる損傷をまとめて覚えると、類似点や違いを整理しやすくなります。例えば、「筋断裂」と「腱断裂」は同じように完全断裂と不完全断裂があるけれど、治療法が異なるという点に注目しましょう。 - 治療法で分類する
治療法に基づいてグループ分けするのもおすすめです。例えば、「完全断裂は基本的に手術が必要、不完全断裂は固定で治療」というように、治療の違いを強調して覚えると記憶に残りやすいです。 - ストーリーで覚える
それぞれの損傷に対して、起こりやすいシチュエーションを想像しながら学習するのも効果的です。たとえば、スポーツで「急に筋肉を使って肉ばなれを起こした」といった具体的なシチュエーションを思い描くと、イメージと一緒に覚えやすくなります。
楽しく、リラックスして学んでいけば、自然と知識が定着しますよ!頑張ってくださいね!
各部位の損傷(1)
頭部損傷
| 病名/損傷 | 特徴・有効な検査・治療法 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 線状骨折 | 血管溝や静脈洞を横切る場合は急性硬膜外血腫のリスクあり。 | 骨折自体の治療は不要。 手術で血腫除去・止血が必要。 |
| 陥没骨折 | 陥没骨が硬膜や脳実質を損傷。 | てんかんや障害がある場合は手術適応。 |
| 頭蓋底骨折 | パンダ徴候(眼周囲出血)、バトル徴候(耳後部出血)、髄液漏、嗅覚脱失・視力障害。 | 基本的に保存的治療。 |
| 鼻骨骨折 | 顔面骨骨折の約30%。斜鼻型・鞍鼻型。 | X線撮影が重要。著しい変形時に整復術(局所/全身麻酔下)。 |
| 眼窩底骨折 | ボールなどで眼球が圧迫され、眼球の上転障害。 | 下眼瞼縁切開で整復、自家骨やシリコンプレートで修復。 |
| 頬骨骨折 | 顔面骨骨折の約20%。一体型が多い。 | 単独骨折なら側頭部切開で整復、眼窩底骨折併発時は複数切開で整復固定。 |
| 下顎骨骨折 | 顔面骨骨折の約50%。筋肉の牽引で骨片が転位。 | 顎間固定と骨折片固定が治療法。 |
| 脳振とう | 衝撃による一過性神経機能障害(気絶)。 | 6時間以内に回復。治療不要、経過観察。 |
| 脳挫傷 | 直撃・反衝・剪力で脳が損傷。出血や浮腫を伴う。 | 重度の場合は減圧開頭術。 |
| 硬膜外血腫 | 線状骨折で硬膜動脈断裂→出血→血腫。脳損傷がなければ予後良好。 | 脳圧迫・脳ヘルニア防止に血腫除去・止血が必要。 |
| 外傷性硬膜下血腫 | 脳実質損傷・脳表面血管出血→血腫形成。予後は損傷の程度次第。 | 大開頭で血腫除去。大脳半球間・頭蓋底部は保存的治療。 |

効率的な暗記法アドバイス
- 語呂合わせ・イメージ化
「パンダの目=頭蓋底骨折」と覚えると、視覚的にイメージが湧きやすい! - カテゴリごとにまとめる
骨折(線状・陥没・頭蓋底)と出血(硬膜外・硬膜下)で分けて覚えると、関連性が見えてきます。 - フラッシュカードを活用する
病名を表に、裏に特徴や治療法を書くと、クイズ感覚で学べます! - 反復学習
一度に覚えようとせず、短時間を何度も繰り返すのがコツです。 - 実際の症例や画像を見る
X線写真や症例動画で実際の症状や手術方法を見ると、記憶がより定着します。
焦らず、少しずつ積み上げていきましょう!
頚部損傷(S10-S19)
| 病名/損傷 | 特徴 | 特記事項 |
|
第1頚椎(環椎)骨折
|
稀な骨折。頭頂部に加わる外力で発生し、後弓の骨折が多い。後頭部痛、頭を両手で支える姿勢が特徴。骨片の転位があれば4~6週間牽引、なければカラーで固定。
|
|
|
第2頚椎(軸椎)骨折
|
頚椎が強く屈曲・伸展される交通外傷で発生。歯突起部骨折が多く、後頭部痛と頚椎可動制限が見られる。牽引整復後、装具固定。軸椎椎弓部骨折(ハングマン骨折)は交通外傷や首吊りで発生。
|
「ハングマン骨折」は首吊り自殺で特徴的。
|
|
頚椎捻挫(むちうち損傷)
|
交通事故で頚部に急加速/減速力が作用し発生。頚部の痛み、圧痛、可動性制限が見られるが、神経症状は少ない。治療はカラー固定、鎮痛剤、温熱療法、牽引療法など。
|
|
|
頚椎過伸展損傷
|
転落、浅いプール飛び込み、交通外傷などで前頭部打撲→頚椎過伸展が原因。黄靭帯が脊髄後索を損傷。前縦靭帯断裂。軽度運動障害から四肢麻痺まで障害は様々。
|
|

暗記のアドバイス
- ストーリーで覚える
各病名ごとに「どんな場面で発生するか」をイメージすると記憶に残りやすいです。例:「交通事故→むちうち」や「首吊り→ハングマン骨折」。 - キーワードに注目する
各特徴から1~2個の重要ワードを抜き出して覚えましょう。例:「環椎=後弓骨折」「軸椎=歯突起部骨折」「むちうち=急加速/減速」。 - 類似点と違いを整理する
例えば、骨折と捻挫の違いを比較しながら覚えると、頭の中で整理しやすくなります。 - 図解を活用する
頚椎の構造や骨折の位置を図で確認すると、視覚的な記憶が深まります。 - 繰り返し声に出す
暗記用テーブルを繰り返し声に出して読むと、記憶が強化されます。特に重要な部分に焦点を当てて、何度も口にするのが効果的です。 - 小テストを作る
自分で簡単なクイズ形式で確認し、記憶を定着させましょう。「第1頚椎骨折の特徴は?」「ハングマン骨折はどこで見られるか?」など。
楽しく学べる工夫を取り入れながら、ぜひ実践してみてください!分からないことがあればまた相談してくださいね 😊
胸部〈郭〉損傷(S20-S29)
| 病名/損傷 | 特徴 | 特記事項 |
| 胸椎骨折(S22) | 強い外力や骨粗鬆症・骨転移性腫瘍で骨強度が低下した場合に発生。椎体が楔状変形や扁平化。治療は対症療法。 | 肋骨が副子の役割を果たすため脊椎の転位は少ない。 |
| 胸骨骨折(S22) | 稀な外傷。自動車運転中のハンドル・ダッシュボード外傷などが原因。合併症に心筋挫傷・心臓破裂・胸大動脈断裂がある。 | 合併症リスクが高いため慎重な観察が必要。 |
| 肋骨骨折(S22) | 最も多い外傷。不全骨折が多いが、気胸・血胸を伴うこともある。動揺胸郭ではドレナージ・気管内挿管による陽圧呼吸が必要。 | 動揺胸郭(flail chest)は呼吸障害を引き起こす。 |
| 心臓損傷(S26) | 銃刀による「穿通性心臓外傷」、鈍的外力による「心筋挫傷」「心破裂」。迅速な外科的治療が不可欠。 | 心タンポナーデ(心膜内出血)は致命的。病院到着前に死亡するケースが多い。 |
| 外傷性気胸(S27) | 肺胞・気管支の損傷により胸腔内に空気が流出。緊張性気胸は胸腔内圧が急激に上昇し、命に関わる。 | 緊張性気胸は早急な胸腔ドレナージが必要。 |
| 外傷性血胸(S27) | 胸腔内に血液が貯留。原因は心損傷・大動脈損傷・肋間動静脈損傷など。 | 胸腔ドレナージにより出血が自然に減少する場合が多い。 |
| 外傷性血気胸(S27) | 胸腔内に血液と空気が同時に貯留。血胸と気胸が同時に発生することが多い。 | 血胸・気胸の合併により症状が悪化しやすい。 |
| 気胸・血胸・血気胸の治療 | 軽度は持続的陰圧吸引で治癒。重度は胸腔ドレナージや開胸手術で肺の縫合・止血を行う。 | 早期のドレナージが救命に直結する。 |

効率よく覚えるためのアドバイス
みなさん、こんにちは!今日は覚えにくい外傷や損傷の知識を、スムーズに覚えるコツをお伝えしますね✨
- イメージで理解する
📖 文章だけではなく、体の構造図や画像を使ってイメージしましょう!
たとえば、肋骨骨折なら「呼吸のたびに痛むイメージ」、緊張性気胸なら「胸にどんどん空気がたまってパンパンになる感じ」を思い浮かべると、ぐっと頭に入ります! - キーワードでまとめる
📝 長文は苦手…という方は、キーワードをピックアップ!
「胸椎骨折=骨粗鬆症・対症療法」
「緊張性気胸=一方向弁・急死」
など、短く区切ってリズムよく覚えましょう♪ - 語呂合わせで楽しく
🤔 たとえば、**動揺胸郭(flail chest)**は「吸気で陥凹、呼気で膨張」。
→「吸ってへこむ、吐いてふくらむ、フレイル胸」なんて語呂合わせもアリです! - ストーリーで覚える
📚 外傷がどう進行するか、ストーリー仕立てにしてみましょう。
「事故で胸骨骨折→心筋挫傷や心破裂が心配→血胸・心タンポナーデになりかけたが、迅速なドレナージで救命!」という流れで覚えると、流れがつかみやすいですよ♪ - 反復してアウトプット!
🗣️ 最後は、覚えたことを声に出してみたり、友達に説明してみましょう!
「気胸と血胸の違いって?」「胸椎骨折の治療は?」とクイズ形式にするのも楽しいです!
💡「暗記=つまらない」ではなく、楽しく覚えて合格へ!
一緒に頑張りましょうね🌸
腹部、下背部、腰椎および骨盤部の損傷
| 病名/損傷 | 特徴 | 特記事項 |
| 骨盤骨折 | 骨盤は強固な構造で、損傷時は臓器損傷や大量出血のリスクがある。バイタルサイン(脈拍・呼吸・血圧)の確認が重要。治療は安静・直達牽引・創外固定が基本。 | 直達牽引・創外固定の使用。 |
| 脾損傷 | 鈍的外力(交通事故、墜落)が原因。腹腔内出血によるショックや腹痛が主症状。CT・超音波で診断。TAE(動脈塞栓術)が有効。 | 摘出はできる限り回避。 |
| 肝損傷 | 腹部外傷で最も多い。鈍的外力が80%。CT・超音波が診断に有効。肝機能検査(AST・ALT)は経過観察に使用。 | CT・超音波が診断の基本。 |
| 膵損傷 | 稀だが重症。CTが有効。膵管損傷はERP(逆行性膵管造影)で確認。保存的治療(絶食・抗生剤・補液)を行うが、重症時は緊急手術。 | ERPで膵管損傷を確認。 |
| 胃損傷 | 鋭的外力が多く、穿孔で腹膜炎とショック。手術(縫合・切除)が必須。 | 手術が絶対適応。 |
| 十二指腸損傷 | 鈍的外力(交通事故)が主因。CTで早期診断。壁内血腫は保存的治療、破裂は手術(縫合・バイパス・切除吻合)。 | 後腹膜破裂は診断が遅れがち。 |
| 小腸損傷 | 鋭的・鈍的外力で損傷。腹痛・腹膜刺激症状。全層性損傷は縫合または切除吻合で手術。 | 緊急手術が必須。 |
| 大腸損傷 | 細菌の多い内容物により、穿孔や破裂で腹膜炎やDICへ進行。縫合・切除吻合、必要なら人工肛門造設。 | 感染管理が重要。 |
| 腎損傷 | 鈍的外力(交通事故)が多い。出血と尿漏れが主症状。CT・超音波で診断。保存療法が基本だが、重症例は手術。 | 他臓器損傷との合併に注意。 |

効率的な暗記方法のアドバイス
みなさん、覚えることが多くて大変ですよね!でもコツを押さえれば、スムーズに覚えられますよ✨
- 関連付けて覚える
似た特徴を持つ疾患をグループ化して覚えると効率的!
例:- 鈍的外力 → 肝損傷・脾損傷・腎損傷
- CTが有効 → 肝損傷・脾損傷・膵損傷
- 語呂合わせを活用
記憶に残りやすい言葉遊びで覚えましょう!
例:「肝(かん)じたらCT(シーティー)」 → 肝損傷はCTで診断! - イラストや図で視覚的に理解
骨盤や腹部臓器の位置関係をイメージすることで、損傷の影響を理解しやすくなります! - 反復学習
一度で覚えようとせず、短い時間で何度も復習するのがカギ!✨ - アウトプット学習
声に出して説明したり、ノートに書き出してみると、より記憶に定着しますよ!
コツコツ積み重ねて、一緒に知識を深めていきましょう😊✨